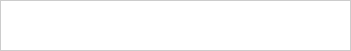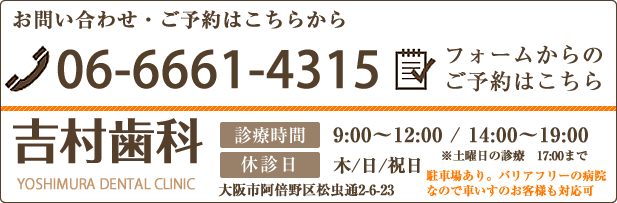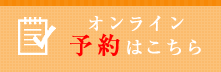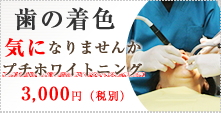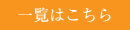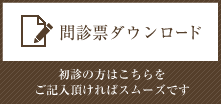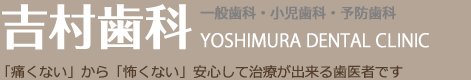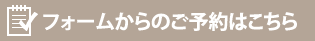漢方治療
漢方治療とは・・・
生薬とは、自然に存在する天然物(植物・動物・鉱物)の全部または一部分で薬効を持つ場合の総称である。
民間薬とは、基本的に1種類の生薬で伝承的あり、用法や用量に決まりがない。
漢方薬とは、数種類の生薬を定められた組み合わせと割合により複合した薬剤であり、方剤と呼ぶ。
漢方薬は本来、煎じ薬や丸薬、散薬として用いるが1976年には、医療用漢方エキス製剤が健保に導入され現在は、これが処方の主流となっている。

漢方治療、製剤について
歯科保険適用エキス製剤
| 歯痛・抜歯後の疼痛・歯齦炎など | 立効散 |
|---|---|
| 口内炎 | 半夏瀉心湯・黄連湯・茵蔯蒿湯 |
| 口渇 | 白虎加人参湯・五苓散 |
| 歯槽膿漏・歯齦炎 | 排膿散及湯 |
※上記製剤以外でも必要な場合は他の漢方を出す事があります。
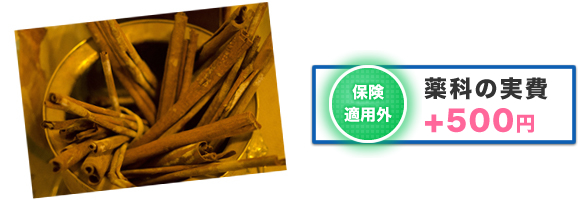
製剤のご案内
| ①立効散(衆方規矩) |
構成生薬 : 細辛、升麻、防風、竜胆、甘草 舌診 : 淡紅から紅、薄苔 |
|---|---|
|
急性の歯痛に対して、証を気にせず投与可能。 アスピリン喘息など、NSAIDsが投与できない場合に使用できる。 細辛の局麻作用があるので、口中で30秒程度もぐもぐした後に服用する。 |
|
| ②半夏瀉心湯(傷寒論・金匱要略) |
構成生薬 : 黄連、黄 、半夏、渇姜、人参、大棗、甘草 舌診 : 厚い白黄苔、やや紅 |
|---|---|
|
上腹部の痞え(心下痞)や嘔気があり、イライラや不眠などの 精神症状も訴えるような場合の上部消化管の炎症をとる方剤。腹がゴロゴロと鳴る下痢。 |
|
| ③黄連湯(傷寒論・金匱要略) |
構成生薬 : 黄連、半夏、乾姜、桂枝、人参、大棗、天草 舌診 : 白膩苔 |
|---|---|
|
心下痞硬よりも心窩部痛を目標とする。上熱下寒 半夏瀉心湯よりはやや急性の消化管の炎症をとる方剤 |
|
| ④茵蔯蒿湯(傷寒論・金匱要略) |
構成生薬 : 茵 蒿、山梔子、大黄 舌診 : 紅、乾燥、黄膩苔 脈診 : 数 |
|---|---|
|
胆汁分泌を改善し、消化管の炎症をとる方剤。 飲食や飲酒の不摂生から、消化管に熱がこもり腹満感や便秘があるような病態に使う。 肝胆湿熱の代表方剤。 |
|
| ⑤五苓散(傷寒論・金匱要略) |
構成生薬 : 茯苓、猪苓、白朮、沢瀉、桂枝 舌診 : 白膩苔 |
|---|---|
|
体内の水の偏在(水毒)を調整する方剤。 口渇・小便不利を目標とする。 |
|
| ⑥白虎加人参湯(傷寒論・金匱要略) |
構成生薬 : 知母、石膏、粳米、人参、甘草 舌診 : 紅、乾燥、黄苔 |
|---|---|
|
体表(肺)の熱をとり、体内の水分の保持に作用する方剤。 口渇・多尿・多汗などを目標とする。 糖尿病患者や、向精神薬などの薬剤性の口渇に有効。 |
|
| ⑦排膿散及湯(金匱要略の排膿湯・東洞経験方) |
構成生薬 : 桔梗、枳実、芍薬、甘草、生姜、大棗 舌診 : 淡紅、苔は厚くない |
|---|---|
|
患部が発赤、腫脹して疼痛を伴った化膿性疾患に対して、全期間にわたり、 消炎排膿的に使用できる方。抗生剤との併用も可。 |
|